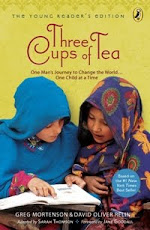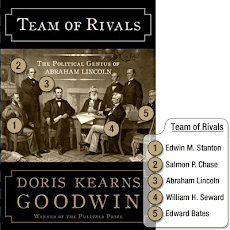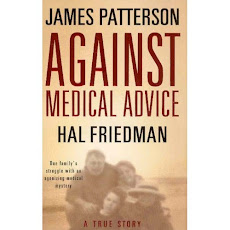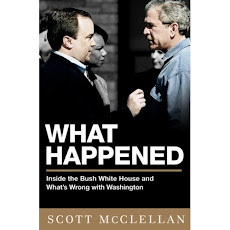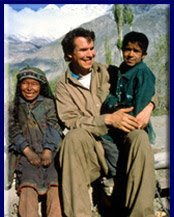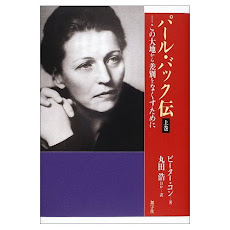(Brian Patton/Bart Robinson 著)
この(息の長い)ガイドブックは、初版1971年以来、今日まで8版(2007年)を重ねているカナディアン・ロッキー案内に関する「聖書」といわれている本である。既に23万部以上が売れている。以前は、写真が白黒だったが、最新版 (約500ページ) は、オールカラーになっている。内容は 250近いハイキング・ルート(距離表示付)、150以上の写真 、 山小屋や交通手段 。カナダ人なら誰でも持っているといわれている定評のある登山(ハイキング)案内書。主に、Banff、Jasper、Yoho、 Kootenay、 Waterton 湖、 Robson 山、Assiniboine 山、 Peter Lougheed、 Elk 湖、Akamina-Kishinena par 等の名所を収録している。 なお著者2人は、地元カナディアン・ロッキー山麓に30年以上住むベテランのハイカー。
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Canadian_Rockies_Trail_Guide
ちなみに、数年前に「山と渓谷社」から、カナダに住む山好きの日本人、益田夫妻が書いた「カナディアン・ロッキーハイキング案内」(約200ページ) が出版されているが、それはもちろん邦訳ではないが、恐らくこの英文原書(聖書)を参考にして、自分たちの山歩き実体験を織り交ぜて、日本人向けに再編したガイドブックであろうと、私は推察する。
http://www.aa.cyberhome.ne.jp/~thashi/2001image/hikingjunbi.htm
私は35年ほど昔、米国(ロッキー山麓にある)コロラド大学に留学研究中、地元の親しい法学部の院生(サンチェス)と一緒に、ロッキー山脈の最高峰「ロングス・ピーク」に登頂したことがあるが、カナディアン・ロッキーには、未だ出かけたことがない。最近、豪州メルボルンにある癌研究所を定年退職し、年金生活を始めたので、好きな本の執筆の合間を利用して、(この「聖書」を片手に) ひとつカナダの山々(ロッキー)にも挑戦してみようと思っている。
2008年4月30日水曜日
2008年4月28日月曜日
原爆開発への「不本意な影の役者」(Leo Szilard)
ハンガリー生まれの科学者レオ・シラード(1898ー1964)は、米国ニューヨーク州生まれのイン テリ政治家フランクリン・ルーズベルト(名大統領)とは、意気投合したが、カン サス州生まれの田舎政治家ハリー・トルーマン(棚ぼた大統領)とは、一線を画した(というか、トルーマンにはシラードの「先見の明」が全く理解できず、彼の忠告を無視し続けた)。
天才的発想の持ち主シラードは、イタリア出身のエンリコ・フェルミ(1938年のノーベル賞受賞者)と、史上初の原子炉をデザイ ンし特許を取るが、ナチスがそれを利用して原爆を製造し、実戦に使用する計画 があることを探知するや、アインシュタインと共に、ルーズベルト宛てに手紙を 書き、米国がナチスよりも先に原爆を開発するよう嘆願した。こうして、「マン ハッタン計画」が開始した。
しかしながら、ナチスは原爆製造計画に失敗したばかりではなく、1945年5 月に降伏してしまう。そこで、シラードは米国の原爆製造計画の中止を提案し始 めた。折悪しく、ドイツの降伏直前に聡明なルーズベルトが急死し、副大統領であったトルー マンが棚ぼた的に大統領に就任した。これが史上最大の悲劇を呼ぶことになった。
ソ連のスターリンに軽く新参者扱いされたトルーマンは、男を上げるために、原 爆を瀕死の日本に落として、スターリンの東欧への進出を牽制しようと図った。 そこで、トルーマン宛ての(降服寸前の日本への原爆投下をせぬよう訴えた)シラードが草稿した 嘆願書は、彼の地元シカゴ大学で研究中の良心的な70名の科学者仲間から署名を得たが、トルーマンや軍部に無視され た。こうして、ヒロシマ・ナガサキに「生き地獄」が発生した。
(良心の呵責を強く感じた)シラードは戦後、反核運動を積極的にリードすると共 に、原子物理学を捨てて、(平和的な)分子生物学研究に専念する。彼はその天才、 情熱、良心のゆえに、ノーベル賞に価する研究をしたにも拘らず、受賞のチャンス を逃し、いわゆる「陰の天才」(1992年出版の評伝のタイトル「Genius in the Shadows」)に甘んじることになる。しかし ながら、我々日本人一人一人が原爆について深く思いをめぐらすとき、シラードの 果した(不本意な)役割がいかに大きかったかを痛感せざるをえないだろう。
ユダヤ人迫害が激しくなる以前(1920年代初頭)、若いシラードは有名なアインシュタインと共に、(当時)科学的研究のメッカであったドイツで、理論物理学の研究を楽しみ、合間には「電磁気ポンプ」を利用した史上初の冷蔵庫などを一緒に考案して特許をとっている。しかしながら、両人共「ユダヤ人」であったので、ヒットラーの台頭と共に、米国に結局亡命せざるをえなくなった。もし仮に、欧州でこの忌まわしいヒットラー戦争が起こらなかったら、彼らの才能はもっと有益な発明発見のために注がれ、恐ろしい「原爆開発」のごとき「天才の浪費」は決して発生しなかったことだろう。「戦争」(集団同士の殺し合い)はどんな理由であれ、もうまっぴら御免だ!
天才的発想の持ち主シラードは、イタリア出身のエンリコ・フェルミ(1938年のノーベル賞受賞者)と、史上初の原子炉をデザイ ンし特許を取るが、ナチスがそれを利用して原爆を製造し、実戦に使用する計画 があることを探知するや、アインシュタインと共に、ルーズベルト宛てに手紙を 書き、米国がナチスよりも先に原爆を開発するよう嘆願した。こうして、「マン ハッタン計画」が開始した。
しかしながら、ナチスは原爆製造計画に失敗したばかりではなく、1945年5 月に降伏してしまう。そこで、シラードは米国の原爆製造計画の中止を提案し始 めた。折悪しく、ドイツの降伏直前に聡明なルーズベルトが急死し、副大統領であったトルー マンが棚ぼた的に大統領に就任した。これが史上最大の悲劇を呼ぶことになった。
ソ連のスターリンに軽く新参者扱いされたトルーマンは、男を上げるために、原 爆を瀕死の日本に落として、スターリンの東欧への進出を牽制しようと図った。 そこで、トルーマン宛ての(降服寸前の日本への原爆投下をせぬよう訴えた)シラードが草稿した 嘆願書は、彼の地元シカゴ大学で研究中の良心的な70名の科学者仲間から署名を得たが、トルーマンや軍部に無視され た。こうして、ヒロシマ・ナガサキに「生き地獄」が発生した。
(良心の呵責を強く感じた)シラードは戦後、反核運動を積極的にリードすると共 に、原子物理学を捨てて、(平和的な)分子生物学研究に専念する。彼はその天才、 情熱、良心のゆえに、ノーベル賞に価する研究をしたにも拘らず、受賞のチャンス を逃し、いわゆる「陰の天才」(1992年出版の評伝のタイトル「Genius in the Shadows」)に甘んじることになる。しかし ながら、我々日本人一人一人が原爆について深く思いをめぐらすとき、シラードの 果した(不本意な)役割がいかに大きかったかを痛感せざるをえないだろう。
ユダヤ人迫害が激しくなる以前(1920年代初頭)、若いシラードは有名なアインシュタインと共に、(当時)科学的研究のメッカであったドイツで、理論物理学の研究を楽しみ、合間には「電磁気ポンプ」を利用した史上初の冷蔵庫などを一緒に考案して特許をとっている。しかしながら、両人共「ユダヤ人」であったので、ヒットラーの台頭と共に、米国に結局亡命せざるをえなくなった。もし仮に、欧州でこの忌まわしいヒットラー戦争が起こらなかったら、彼らの才能はもっと有益な発明発見のために注がれ、恐ろしい「原爆開発」のごとき「天才の浪費」は決して発生しなかったことだろう。「戦争」(集団同士の殺し合い)はどんな理由であれ、もうまっぴら御免だ!
型破りの女 (Jean Tahija)
ジーン・タヒヤ (1916ー2001)が自伝を出版してから、もう10年ほどの月日が経つ。彼女は豪州メルボルン生まれの白人女性で、歯科医だったが、太平洋戦争中にインドネシア (オランダ領東インディー ) から軍事訓練のため、メルボルンに派遺され、ジーンのウオルター家に食事に招かれたある若いハンサムな将校に初対面して以来、熱烈なロマンスが芽生え、戦後まもなく、そのインドネシア将校(ジュリウス・タヒヤ)と結婚して、親元を離れ、はるばる異国の首都ジャカルタに移民する。白豪主義がまだ強かった当時としては、型破りのロマンスだった。1946年にメルボルンの地方紙に「褐色のヒーローが白人の妻と結ばれる」という記事が掲載された。ジーンが新聞社に強く抗議して、(皮膚の色を表わす)形容詞を記事から削除するよう要求したので、新聞社は渋々、見出しを書き換えざるをえなかった。
ジーンの父親は警察官だったが、進歩的な物の考え方の持ち主だった。娘に口癖のようにこう言っていた。「女性も男性同様、キャリアを持つ権利がある。医師か歯科医になるよう頑張りなさい!」。ジーンは1941年に、メルボルン大学卒業生の中で、史上初めての女性歯科医になるという、歴史的な快挙を成し遂げた。さて、将来の夫ジュリウスに会ったのは、その翌年だった。彼は戦争中、祖国インドネシアの独立をめざして、スカルノ(独立後の初代大統領)の指揮下、日本軍やオランダ軍と勇敢に戦っていた。「ヒーロー」の由縁はそこにあった。
1945年の日本敗戦後も、スカルノのインドネシア軍は、オランダ軍に対して血みどろのゲリラ戦を展開した。ジーンは豪州人ながら、夫の独立戦争を助けて、1949年に独立が正式に承認されるまで、共に戦い抜いた。さて独立当時、(イスラム教の影響が強い)インドネシアには女性の歯科医は皆無だった。しかしながら、夫ジュリウスも進歩的な考えの持ち主で、ジャカルタの病院で、ジーンが歯科医を続けることを激励した。ジュリウスは祖国独立後、スカルノ政権の高官を務めるばかりではなく、石油会社「カルテックス」の重役として活躍した。夫婦の間に聡明な息子が2人生まれた。
私がこの型破りな女性ジーンに初めて会ったのは、彼女の自伝が出版されて間もなく、私の自宅から歩いて2、3分の所にある夫婦の別荘に、彼女がしばらく振りに訪れた折だった。それから、2、3年後、ジュリウスから、ジーンがとうとう病死したという悲報を受け取った。夫であるインドネシア人と共に、独立運動のために体を張った、稀れにみる勇気のある豪州女性だった。
蛇足だが、定時制高校を中退して、赤坂界隈の美人ホステスになり、日本の石油貿易商社からの賄賂(「夜のプレゼント」)として1960年頃、ジャカルタへ派遺され、スカルノ大統領の第3夫人になったデヴィ夫人(旧姓、根本 七保子)は、背後の事情を薄々知っていたジーン(タヒヤ夫人)自身を含めてインドネシア大衆の間には余り馴染みがなかったようである。
ジーンの父親は警察官だったが、進歩的な物の考え方の持ち主だった。娘に口癖のようにこう言っていた。「女性も男性同様、キャリアを持つ権利がある。医師か歯科医になるよう頑張りなさい!」。ジーンは1941年に、メルボルン大学卒業生の中で、史上初めての女性歯科医になるという、歴史的な快挙を成し遂げた。さて、将来の夫ジュリウスに会ったのは、その翌年だった。彼は戦争中、祖国インドネシアの独立をめざして、スカルノ(独立後の初代大統領)の指揮下、日本軍やオランダ軍と勇敢に戦っていた。「ヒーロー」の由縁はそこにあった。
1945年の日本敗戦後も、スカルノのインドネシア軍は、オランダ軍に対して血みどろのゲリラ戦を展開した。ジーンは豪州人ながら、夫の独立戦争を助けて、1949年に独立が正式に承認されるまで、共に戦い抜いた。さて独立当時、(イスラム教の影響が強い)インドネシアには女性の歯科医は皆無だった。しかしながら、夫ジュリウスも進歩的な考えの持ち主で、ジャカルタの病院で、ジーンが歯科医を続けることを激励した。ジュリウスは祖国独立後、スカルノ政権の高官を務めるばかりではなく、石油会社「カルテックス」の重役として活躍した。夫婦の間に聡明な息子が2人生まれた。
私がこの型破りな女性ジーンに初めて会ったのは、彼女の自伝が出版されて間もなく、私の自宅から歩いて2、3分の所にある夫婦の別荘に、彼女がしばらく振りに訪れた折だった。それから、2、3年後、ジュリウスから、ジーンがとうとう病死したという悲報を受け取った。夫であるインドネシア人と共に、独立運動のために体を張った、稀れにみる勇気のある豪州女性だった。
蛇足だが、定時制高校を中退して、赤坂界隈の美人ホステスになり、日本の石油貿易商社からの賄賂(「夜のプレゼント」)として1960年頃、ジャカルタへ派遺され、スカルノ大統領の第3夫人になったデヴィ夫人(旧姓、根本 七保子)は、背後の事情を薄々知っていたジーン(タヒヤ夫人)自身を含めてインドネシア大衆の間には余り馴染みがなかったようである。
2008年4月27日日曜日
地球を逆転させた生物学者(David Baltimore)
「例外のない法則はない」という言葉が私は大好きだ。権威に盲従することを好まぬ私の強い気性からだ。さて、1950年代にワトソンとクリックが遺伝子DNAのらせん構造解析から、「DNAがRNAを作り(転写)、さらにRNAが蛋白質を作る(翻訳)」といういわゆる分子生物学の「セントラル・ドグマ」を提唱、確立した。
しかしながら、1970頃に、発癌性のRNAウイルス(レトロウイルス)を研究していた2人の学者、デビッド・ボルチモアとホワード・テミンが、この法則に従わない現象を発見した。これらの発癌性ウイルスは逆に、自分のRNAを鋳型にして、それと相補的なDNAを、宿主細胞内で、自らの特殊な酵素を使って、転写する機能を持つことを見つけた。そして、この不思議な酵素を「逆転写酵素」と名付けた。つまり、「RNAがDNAを作る」という例外をウイルスの世界で発見して、従来の世界観を、逆転したわけである。5年後に、彼らのこの逆転劇に対して、ノーベル賞が与えられた。
実は、この逆転劇は、人々の「物の考え方」を一変したばかりではなく、1980年代に、新しい革命的なテクノロジー(組み替え工学)を、分子生物学の世界に産み出した。「逆転写酵素」を使って、自由自在に遺伝子をクローンできるようになったばかりではなく、その遺伝子をある種から他の種に移植することもできるようになった。原理的には、この方法によって、癌などの難病の遺伝子療法が遠い将来、可能になるわけだ。例えば、発癌の原因の1つは、正常細胞にあった抗癌遺伝子が変異によって、機能を失うことによる。従って、癌細胞に正常な抗癌遺伝子を挿入し補ってやれば、癌は治るはずである。
しかしながら、今日の技術レベルでは、患者の体内に巣くう全ての癌細胞に、抗癌遺伝子を効率よく挿入することが、まだ難しい。そこで、この抗癌遺伝子産物(蛋白)の機能と良く似た薬理作用を持つ化合物を見つけ、制癌剤として開発することが、我々「癌学者」の目下の緊急な課題になっている。我々が開発中の一連のPAK遮断剤は、抗癌蛋白「メルリン」がPAKという発癌性酵素 (キナーゼ) を阻害するという、最近の発見に基づいて進められているものである。合成物質ばかりではなく、天然物 (例えば、抗生物質FK228、赤ブドウ、蜜蜂の作るプロポリスなど) にも、PAKを遮断する作用があるという事実は、大変面白い。
さて、ボルチモアの英知は、科学の分野のみに留まらない。彼は「男女共生」の情熱的な推進者でもあり、「逆転写酵素」の発見にも一部貢献した同僚で、中国出身のアリスを生涯の伴侶として選んだ。さらに、米国政府が戦後始めた2つのいわゆる「出口なき泥沼戦争」、ベトナム戦争とイラク戦争、の継続に強く反対している。数年前に出版されたボルチモアに関する評伝(「Ahead of the Curve」) から、多くの若い読者たちが、権威や先入観に捕らわれぬ彼の「自由な発想法」を会得できれば、誠に幸いである。
しかしながら、1970頃に、発癌性のRNAウイルス(レトロウイルス)を研究していた2人の学者、デビッド・ボルチモアとホワード・テミンが、この法則に従わない現象を発見した。これらの発癌性ウイルスは逆に、自分のRNAを鋳型にして、それと相補的なDNAを、宿主細胞内で、自らの特殊な酵素を使って、転写する機能を持つことを見つけた。そして、この不思議な酵素を「逆転写酵素」と名付けた。つまり、「RNAがDNAを作る」という例外をウイルスの世界で発見して、従来の世界観を、逆転したわけである。5年後に、彼らのこの逆転劇に対して、ノーベル賞が与えられた。
実は、この逆転劇は、人々の「物の考え方」を一変したばかりではなく、1980年代に、新しい革命的なテクノロジー(組み替え工学)を、分子生物学の世界に産み出した。「逆転写酵素」を使って、自由自在に遺伝子をクローンできるようになったばかりではなく、その遺伝子をある種から他の種に移植することもできるようになった。原理的には、この方法によって、癌などの難病の遺伝子療法が遠い将来、可能になるわけだ。例えば、発癌の原因の1つは、正常細胞にあった抗癌遺伝子が変異によって、機能を失うことによる。従って、癌細胞に正常な抗癌遺伝子を挿入し補ってやれば、癌は治るはずである。
しかしながら、今日の技術レベルでは、患者の体内に巣くう全ての癌細胞に、抗癌遺伝子を効率よく挿入することが、まだ難しい。そこで、この抗癌遺伝子産物(蛋白)の機能と良く似た薬理作用を持つ化合物を見つけ、制癌剤として開発することが、我々「癌学者」の目下の緊急な課題になっている。我々が開発中の一連のPAK遮断剤は、抗癌蛋白「メルリン」がPAKという発癌性酵素 (キナーゼ) を阻害するという、最近の発見に基づいて進められているものである。合成物質ばかりではなく、天然物 (例えば、抗生物質FK228、赤ブドウ、蜜蜂の作るプロポリスなど) にも、PAKを遮断する作用があるという事実は、大変面白い。
さて、ボルチモアの英知は、科学の分野のみに留まらない。彼は「男女共生」の情熱的な推進者でもあり、「逆転写酵素」の発見にも一部貢献した同僚で、中国出身のアリスを生涯の伴侶として選んだ。さらに、米国政府が戦後始めた2つのいわゆる「出口なき泥沼戦争」、ベトナム戦争とイラク戦争、の継続に強く反対している。数年前に出版されたボルチモアに関する評伝(「Ahead of the Curve」) から、多くの若い読者たちが、権威や先入観に捕らわれぬ彼の「自由な発想法」を会得できれば、誠に幸いである。
2008年4月26日土曜日
自伝「チャイナ・ガール」(Helene Chung)
豪州メルボルンの我々の自宅から数軒先に住む元ABCテレビ局の海外(北京)特派員ヘレン・チュングが綴った赤裸々な自伝が最近出版された (なんと「キャッチフレーズ」には、修道院の尼さんには決して読ませられない内容がある、という注釈つきの問題作だ)。十数年前に、夫のジョン・マーチンが癌の転移で亡くなって以来、母親と一緒にひっそりと暮らしていたが、実は回想録を書いていたことを、我々は知らなかった。
ヘレンは戦後まもなく、豪州タスマニア島の首都ホーバートで中国系の両親の間に生まれた。カトリック系の女学校に通っていた当時 (1950年代) の豪州では、いわゆる「白豪主義」がまだ根強く、クラスの大部分を占める(金髪で青い目の)白人同級生から、「Ching Chong チャイナ・ガール!」とはやし立てられたことから、この回想録のタイトルが生まれた。彼女には、他人には打ち明け難い悩みがもう1つあった。自分の母親が、夫と離婚後、生計のために、ヌード・モデルをしているというショッキングな事実を知っていたからだ。
そんな「イジメ」や心の悩みにも敗けず、聡明なヘレンは、大学時代で頭角を現わし、ジャーナリズムに興味をもち始め、海外をかけ巡っている内に、豪州のテレビ局「ABC」(日本のNHKに相当する)で、有色人種で初めてテレビ・キャスターに採用され、間もなく女性として初の海外特派員として、北京に駐在するようになった。
さて、1963年に彼女がタスマニア大学の学生時代、同期生のジョン・マーチンに初めて出会った。それから13年後の1976年に、彼がメルボルンの郊外にあるゴードン工科大学(歴史学)の講師をしていたころ、ABCのホーバート支局でレポーターをしていたヘレンに、仕事で偶々、ジョンとインタービューをするチャンスが訪れる。それがきっかけで、以来ロマンスの花が咲き、2人は結婚へゴールインする。1991年にジョンが大腸癌にかかっていることが判明し、手術で癌は一旦取り除かれたが、2年後にそれが骨盤に転移していることが発見され、治療のかいもなく、とうとう他界した。1995年に、彼の死を悼む「我が優しのジョン」を、ヘレンが出版している。
ヘレンは戦後まもなく、豪州タスマニア島の首都ホーバートで中国系の両親の間に生まれた。カトリック系の女学校に通っていた当時 (1950年代) の豪州では、いわゆる「白豪主義」がまだ根強く、クラスの大部分を占める(金髪で青い目の)白人同級生から、「Ching Chong チャイナ・ガール!」とはやし立てられたことから、この回想録のタイトルが生まれた。彼女には、他人には打ち明け難い悩みがもう1つあった。自分の母親が、夫と離婚後、生計のために、ヌード・モデルをしているというショッキングな事実を知っていたからだ。
そんな「イジメ」や心の悩みにも敗けず、聡明なヘレンは、大学時代で頭角を現わし、ジャーナリズムに興味をもち始め、海外をかけ巡っている内に、豪州のテレビ局「ABC」(日本のNHKに相当する)で、有色人種で初めてテレビ・キャスターに採用され、間もなく女性として初の海外特派員として、北京に駐在するようになった。
さて、1963年に彼女がタスマニア大学の学生時代、同期生のジョン・マーチンに初めて出会った。それから13年後の1976年に、彼がメルボルンの郊外にあるゴードン工科大学(歴史学)の講師をしていたころ、ABCのホーバート支局でレポーターをしていたヘレンに、仕事で偶々、ジョンとインタービューをするチャンスが訪れる。それがきっかけで、以来ロマンスの花が咲き、2人は結婚へゴールインする。1991年にジョンが大腸癌にかかっていることが判明し、手術で癌は一旦取り除かれたが、2年後にそれが骨盤に転移していることが発見され、治療のかいもなく、とうとう他界した。1995年に、彼の死を悼む「我が優しのジョン」を、ヘレンが出版している。
人格の尺度 (Sidney Poitier)
米国の黒人俳優の中で、史上初めてアカデミー賞を獲得したシドニー・ポアチエのベストセラー自伝が数年前に出版された。英文原書のタイトルは、「The Measure of a Man」。彼の主演映画で、私が最も感銘したのは、1963年の名作「野のユリ」(Lilies of the Field) だった。戦後、ドイツから米国に移民してきた修道院の尼さんたちを助ける、歌のとても好きな(ホームレスの)青年役を演ずる。翌年、彼はこのすばらしい演技で最優秀男優賞 (オスカー) をもらった。この自伝では、自分自身の人生を振り返りながら、単に映画俳優としてばかりではなく、人間として、特に息子として、夫として、あるいは父親として、自分が一体どれだけの価値があったかを、厳しく自己評価しつつ、自分の生き甲斐を率直に、我々に語りかけている。
ポアチエは、少年時代を、生地のバハマ諸島のキャット (猫) 島で、両親と共に、貧しいが平穏な日々を過ごした。この島には、電灯や水道などのいわゆる「文明の力」がほとんどなかった。トマト栽培が主な産業だった。ところが、1936年になって、米国大陸のフロリダ州へのトマトの輸出が禁止されたため、島の経済はとうとう破綻をきたした。そこで、15歳になって、彼は親元を離れ、フロリダ州マイアミに単身(裸一貫で)移住し、白人世界に初めて入り、数々の波乱豊かな冒険生活を始める。兵役志願、ホテルのウエイターなどで苦い経験を経たのち、結局黒人差別の少ないニューヨーク市のハーレム(貧民窟)にある黒人劇場に、俳優になる訓練を受け始める。1955年に、グレン・フォードと共演で、「黒板ジャングル」という映画に初デビューし、正義感の強い若き黒人教師の役を熱演する。以来、正義感、情熱、思いやりのある人物が、彼の好きな役柄になる。
さて、40年近く映画界ですばらしい経歴を積んだのち、ポアチエの人生にも危機がやってきた。1993年、70歳にさしかかる頃、前立腺癌という診断を受けた。しかしながら、幸いにも比較的早期だったので、手術で難を逃れた。その後数年間、癌の再発の可能性を懸念し続けていたが、幸い、再発の兆候はみられず、ほっと安心して、自伝の執筆を始めたわけである。
************************************************************************************
1943年頃、ポアチエが16歳そこそこでマイアミに移住してきて間もなく、身の毛がよ立つような恐ろしい体験をしたそうだ。
ある日の夜遅く、私は白人の住む地区を訪れる羽目に陥った。その翌日、旅行に出かける予定で背広のドライクリーニングを頼んでおいたが、最寄りの(黒人住民地区にある)クリーニング屋にはまだ届いていなかった。そこで、バスで町はずれのクリーニング工場まで取りに出かけざるをえなかった。ところがバス停に戻って来ると、最終便が既に出たあとだった。そこで、黒人地区方面に向かう車を見つけて、できればヒッチハイクで帰宅する積りだった。もちろん黒人がドライバーの車だけを探し始めた。最初に停まってくれた車は、なんと私服のパトカーだった。ところが不幸にして、乗っていたのはなんと白人の運ちゃんだった。警官が車の窓を開けて、私にこう指図した。「おいガキ、そこの路地に入れ!」 。パトカーが私を路地に先導した。
路地には人影が全くなかった。「これはやばい」と私はとっさに判断した。そこで何が起ころうと目撃者が誰もいない。パトカーの窓からピストルの銃口が私の頭をピタリと狙っているのに気づいた。パトカーから2人の警官の会話が聞こえてきた。
「奴をどう料理してやろうか?」
「こんな所で一体何をしているのか、調べてみようじゃないか」
「奴をここで射殺してやろうか?」
会話の内容が穏やかではない! 私は背筋に戦慄を感じると同時に、弱い者苛めの警官たちに対して、かっと怒りを禁じえなかった。私は状況を察して、出来るだけ冷静に、自分がなぜこんな所に来たかを説明した。
「よしわかった。それなら帰宅してもいいが、ここからずっと歩いて帰るんだ。ただし、一度でも後ろを振り返ってみろ、頭にズドンだぞ! 覚悟はいいか?」
「了解しました」
「それなら、さっさと歩け! 直ぐ後ろから車で尾行してやる」
私はすばやく路地から抜け出して、バス道路を歩き始めた。家まで延々50ブロックもある道のりを、決して後ろを振り向かずに。。。
頭を前方に真っ直ぐ固定して、目だけを左右にキョロキョロ動かしながら、通りの店の窓ガラスに写るパトカーの影を時々チェックしながら。。。「戦慄」の尾行は、私が親戚と一緒に住む家がある(黒人地区の)路地に入るまで、たっぷり50ブロック間断なく続いた。そして、私が最後に「救い」の角を曲がったとたん、パトカーがすっと姿を消した。
ポアチエは、少年時代を、生地のバハマ諸島のキャット (猫) 島で、両親と共に、貧しいが平穏な日々を過ごした。この島には、電灯や水道などのいわゆる「文明の力」がほとんどなかった。トマト栽培が主な産業だった。ところが、1936年になって、米国大陸のフロリダ州へのトマトの輸出が禁止されたため、島の経済はとうとう破綻をきたした。そこで、15歳になって、彼は親元を離れ、フロリダ州マイアミに単身(裸一貫で)移住し、白人世界に初めて入り、数々の波乱豊かな冒険生活を始める。兵役志願、ホテルのウエイターなどで苦い経験を経たのち、結局黒人差別の少ないニューヨーク市のハーレム(貧民窟)にある黒人劇場に、俳優になる訓練を受け始める。1955年に、グレン・フォードと共演で、「黒板ジャングル」という映画に初デビューし、正義感の強い若き黒人教師の役を熱演する。以来、正義感、情熱、思いやりのある人物が、彼の好きな役柄になる。
さて、40年近く映画界ですばらしい経歴を積んだのち、ポアチエの人生にも危機がやってきた。1993年、70歳にさしかかる頃、前立腺癌という診断を受けた。しかしながら、幸いにも比較的早期だったので、手術で難を逃れた。その後数年間、癌の再発の可能性を懸念し続けていたが、幸い、再発の兆候はみられず、ほっと安心して、自伝の執筆を始めたわけである。
************************************************************************************
1943年頃、ポアチエが16歳そこそこでマイアミに移住してきて間もなく、身の毛がよ立つような恐ろしい体験をしたそうだ。
ある日の夜遅く、私は白人の住む地区を訪れる羽目に陥った。その翌日、旅行に出かける予定で背広のドライクリーニングを頼んでおいたが、最寄りの(黒人住民地区にある)クリーニング屋にはまだ届いていなかった。そこで、バスで町はずれのクリーニング工場まで取りに出かけざるをえなかった。ところがバス停に戻って来ると、最終便が既に出たあとだった。そこで、黒人地区方面に向かう車を見つけて、できればヒッチハイクで帰宅する積りだった。もちろん黒人がドライバーの車だけを探し始めた。最初に停まってくれた車は、なんと私服のパトカーだった。ところが不幸にして、乗っていたのはなんと白人の運ちゃんだった。警官が車の窓を開けて、私にこう指図した。「おいガキ、そこの路地に入れ!」 。パトカーが私を路地に先導した。
路地には人影が全くなかった。「これはやばい」と私はとっさに判断した。そこで何が起ころうと目撃者が誰もいない。パトカーの窓からピストルの銃口が私の頭をピタリと狙っているのに気づいた。パトカーから2人の警官の会話が聞こえてきた。
「奴をどう料理してやろうか?」
「こんな所で一体何をしているのか、調べてみようじゃないか」
「奴をここで射殺してやろうか?」
会話の内容が穏やかではない! 私は背筋に戦慄を感じると同時に、弱い者苛めの警官たちに対して、かっと怒りを禁じえなかった。私は状況を察して、出来るだけ冷静に、自分がなぜこんな所に来たかを説明した。
「よしわかった。それなら帰宅してもいいが、ここからずっと歩いて帰るんだ。ただし、一度でも後ろを振り返ってみろ、頭にズドンだぞ! 覚悟はいいか?」
「了解しました」
「それなら、さっさと歩け! 直ぐ後ろから車で尾行してやる」
私はすばやく路地から抜け出して、バス道路を歩き始めた。家まで延々50ブロックもある道のりを、決して後ろを振り向かずに。。。
頭を前方に真っ直ぐ固定して、目だけを左右にキョロキョロ動かしながら、通りの店の窓ガラスに写るパトカーの影を時々チェックしながら。。。「戦慄」の尾行は、私が親戚と一緒に住む家がある(黒人地区の)路地に入るまで、たっぷり50ブロック間断なく続いた。そして、私が最後に「救い」の角を曲がったとたん、パトカーがすっと姿を消した。
2008年4月22日火曜日
NF2患者の手記 「難病NFは私を強くした」 (Jane Wilson)
2005年に、NFの重症患者ジェーンがパソコンを使って、英文手記(約100ページ)を自費出版した(原書のタイトルは、「Who Am I?」)。ジェーンは、米国アイオワ州に住む1952年11月生まれの中年の女性(詩人)で、17歳の誕生日を迎えてまもなく、最初の脳腫瘍手術を受ける。以後、この得体の知れぬ脳腫瘍のため、半世紀にわたり5回の脳手術をせざるをえなくなる。現在、両耳が全く聴こえず、片目だけが見え、チューブを通して、流動食を食べながら、車椅子の生活を続けている。両親、夫、弟は既に他界したが、まだジェーンには一人娘(ハイジ)と2人の孫がいる。ごく最近、やはり車椅子生活をする老人と再婚したという明るいニュースが私のもとに届いた。実はこの彼が、ジェーンの手記の製本を一手に引き受けてくれたそうだ。NFをめぐる世界には「鬼」もいれば「仏」もいるようだ。
さて、ジェーンの不可解な難病が、実はNF2であることが初めて判明したのは、1996年になってからで、NF1とNF2との区別がはっきりしてから、既に10年近い月日が経っていた。なお、ジェーンの脳腫瘍が初めて発見された1969年には、「NF2」という難病の概念は、医学の世界にまだなかった。以下は、今から12年前の脳手術(4回目)に関するストーリー(抜粋)である。
1995年2月、父さんが死んだのち、母さんは「独り暮らしはごめんだ」と言い始めた。そこで、私も母さんもそれぞれ、家や家具などを売り払い、その年の8月、アイオワ州の西バーリントンにある小さな家を買った(掃除が簡単になった!)。そして、私のために、通路にてすりを付けてもらった。私はまだ、杖なしに歩いていたが、それがだんだんきつくなり始めていたからだ。てすりのおかげで、歩行がずっと楽になった。
まもなく、10月になって、私がオルガン奏者として働いていた教会の牧師がとうとう亡くなった。私のよき親友だった。11月に私は、新しい車を買った。その一週間後に、我々3人(父さん、母さん、私)が売り払った要約会社の新しい経営者陣から、会社を売却したから、従業員を全員解雇したと言われた。彼らは、母さんと私に、最後の給料を払ったのち、首にした。たった2週間前の通告しかくれなかった。我々は皆、とても裏切られた気持になった。不幸中の幸いは、要約業者で競争相手だった会社に、私が顔を出したら、その場で、私を雇ってくれたことだった。この会社はその昔、父さんや母さんが働いていたところだった。その後、1963年に両親がそこから独立して、自分たちの会社を始めたという面白いいきさつがあった。ある意味で、一周回って、元の古巣に戻ってきたという感じだ。新しい職場では、給料も増えたし、色々な恩恵があった。その1つは、グループ健康保険で、次の私の手術代をカバーしてくれた。私は新しい上司に、聴覚と平均感覚を失いつつあり、いつかはつんぼになり、杖をついて歩かねばならなくなる日が来ることを、予め話した。それでも、彼は私を採用してくれた。彼はとても善良な人間だった! だから、彼と仕事をするのが好きになった。
1996年の夏、補聴器を交換するために、何度もUIHC(アイオワ大学ヘルスセンター)に通院し始めた。晩夏に、とうとう私の聴覚が消えかかってきたので、眼科、OTO科、脳外科など色々な分野の医者たちから精密検査を受けた。そして結局、長らく患っていた私の病気が、なんと稀少難病「NF2」 (神経線維腫症2型)であると宣告された。私はショックを受けたいうよりは、むしろホッとした。というのは、なぜ私に脳腫瘍があり、平均感覚や聴覚が失われたのかが、はっきりし始めたからだ。ショックはあとでやってきた。ジワジワと身体を衰弱させる「不治」の (いまだに根治の方法が見つかっていない) 病であることが、わかったからだ。
母さんが私の4度目の脳手術についてきてくれた。それはその年の11月、私の孫ジェーソン2世が生まれてから8日後のことだった。 私はABI(聴覚脳幹インプラント、俗称「電子耳」)の挿入に同意した。ABIは当時まだ試験的なもので、UIHCでは私が3人目のモルモットだった。聴神経上の腫瘍が脳外科医のアーノルド・メネゼス博士によって除去されたのち、OTO医師ブルース・ガンツ博士によって、ABIが移植されることになった。
15時間半の手術後、ICU (集中治療室) にいる間、私は両足に感覚が全くなかった。一時的に腰から下が麻痺していた。もちろん、私は吐き気をもよおした。この吐き気は、今や脳手術後の自然現象になってしまった! 「 脳の中に挿入されたABIの位置が変わらぬように、できるだけ直立したまま吐くように」と医者から忠告された。足に感覚がないのは、麻酔のせいであることもわかった。 麻酔が切れるまで、かなり時間がかかった。あとで知ったことだが、摘出した腫瘍は1つのみではなく、3つもだった。それで、あんなに手術が長びいたのだ。また左の顔面が部分的に麻痺していた。しばらくして、一部の動きは回復してきたが、他の機能は不可逆的に失われた。
私が歩行不能になっていたので、両脚の血液循環を促進するための足ポンプを、医師が注文してくれた。明らかに、私はどこへも行けなくなった! 普通の食事もまた食べられなくなった。流動食からベビーフード、そして「ピューレ」へという食生活を、再び繰り返すことになった。看護婦たちが初めて私を散歩に連れ出してくれたとき、私の膝は両方とも、あたかも天に昇っていくかのように感じた。両側から支える看護婦たちに向かって、私は冗談を吐いたものだ。
「私は宇宙飛行士としては失格ね。無重力の世界では歩けないから」
私がまだ入院中に、母さんもぐあいが悪くなり、すぐ下の階に入院することになった。そこで、私は車椅子で、母さんの病室を訪ねた。私の脳手術から2週間半後に、2人ともそろって退院になった。私はまだ独りでは、歩けなかった。24時間ケアが必要だった。それに、2、3週間、物療(フィジオ)が必要だと、医師たちに忠告された。
2週間以内に、手術のために母さんがまた病院に戻らざるをえなくなった。そこで、母さんが数人の友達に頼んで、私のケア(看護)をアレンジしてくれた。私は、まだ歩行が不自由だったので、独りぼっちにはしておけなかったからだ。母さんの手術はうまくいった。そして、私も松葉杖をつけば、トイレまで独りで行けるようになった。しかしながら、前かがみがまだできなかったので、用を済ませた後、自分の始末ができず、友人の手をわずらわせざるを得なかった。
やがて、杖を頼りに独りで歩けるようになったので、毎日2時間の散歩を始めた。
これが我々多くのNF2患者の健康回復への道筋だった。とても時間がかかる。その間 (半年ほど)、我々は給料なしになり、最小限の生活を余儀なくされる。その後、フルタイムで働き始め、また車を運転し始める。しかし、7年後に訪れた(最後の)手術は、私の人生を「永遠」(不可逆的)に変えることになる。。。
解説: 「NF」(多発性神経線維腫)の発見から、治療薬の開発まで
通称「レック」(正式には、「レックリングハウゼン氏病」あるいは「NF1」) の最初の発見者は、ドイツの病理学者、フリードリッヒ・フォン・レックリングハウゼン(1833ー1910)である。彼は有名な病理/生理学者ルドルフ・ヴィルショウ(1821ー1902)の弟子の一人であるが、ストラスブルグ大学の学長をやっていた1882年に、この難病を初めて発見し、「皮膚の多発性線維腫と多発性神経腫との関係について」 という題名の歴史的な論文を発表した。
従って、2007年は、この難病の発見から125年目を迎えることになる。そろそろ、この難病の治療(特効)薬が開発され、市販されても、不思議ではない、と素人、特にこの難病に始終悩まされている患者たちやその家族が期待するのは無理からぬことである。しかしながら、その現実はかなり厳しい。
まずその病因が判明するまで、遅々として1世紀以上かかったからである。まず類似したように見える2種類のNF、つまりNF1とNF2との遺伝学的な区別がはっきり確立したのが1987年だった。当時、ボストンのハーバード大学付属病院、マサチューセッツ総合病院(MGH)勤務のバーント・サイジンガーらが、NF1病因遺伝子は、17番目の染色体にあり、NF2病因遺伝子は、22番目の染色体にあることを、初めてつきとめた。
NF2(神経線維腫症 2型)とは何か?
NF2は、シュワノーマ (神経鞘腫) とメニンジオーマ(髄膜腫)に代表される神経あるいは脳腫瘍を伴う難病で、その病因は、NF2と呼ばれる一対の遺伝子の両方が不活性化され、その遺伝子産物である「メルリン」と呼ばれる抗癌蛋白が正常な機能を発揮できなくなることによる。NF2患者の約半数は、親からの遺伝(つまり、片方の親のNF2遺伝子に変異があると、50%の確率で、その変異が子にも遺伝する)。他の半数は「孤発」といって、親の遺伝子状態とは無関係に、受精の初期に起こったNF2遺伝子上の変異によって発症する。NF2の発症頻度は、人口約3万人に1人といわれている。だから、稀少難病の1つと数えられている。
NF2の診断に今日最もよく使われている標準的な症状は、両側性前庭神経鞘腫 (シュワノーマ) である。最初の典型的な前駆症状は、耳鳴り、難聴、平均感覚の消失、視力の低下あるいは2重映像などである。最終的な判断には、NF2遺伝子診断や脳あるいは背骨のMRI診断などの精密検査が必要になる場合がある。
例えば、頻繁に視神経に障害をもたらす脳腫瘍「メニンジオーマ」の場合、半数以上はNF2であるが、残りの半数近くは、全く別の病因であることがわかっている。また、NF2患者の場合、健康人に比べて、アスベストによる悪性中皮腫(肺癌)の発生率が2倍以上になることが、最近報告されている。
NF2は、類似の稀少難病であるNF1(神経線維腫症 1型)とどう違うのだろうか? まずNF1は、カフェオレ班 (コーヒー色の斑点で腫瘍ではない!)、あるいはニューロフィブローマ(神経線維腫)やMPNST(悪性末梢神経鞘腫) に代表される表皮、内皮あるいは神経に発症する腫瘍を伴う難病である。さらに、NF1の病因は、NF1と呼ばれる一対の遺伝子の両方が不活性化され、その遺伝子産物(「RAS GAP」の一種で、抗癌蛋白)が、正常な機能を発揮できなくなることによる。NF1の発症頻度は、人口約3千人に1人といわれている。だから、NF2の発症頻度の10倍ほど高い。NF1の大半(9割)は、良性腫瘍で命に別状はないが、MPNSTを含む残りの1割は、死に至る悪性腫瘍(癌)である。MPNSTの5年生存率は、20%前後といわれている。
1990年になって、そのNF1「病因遺伝子」が単離された。つまり、NF1という抗癌遺伝子が変異によって、その機能を失うと、この難病に伴う種々の神経線維腫(NF)が発症しやすくなるということが判明した。更に、NF2の病因遺伝子である別の抗癌遺伝子(NF2)が、1993年になって単離された。従って、この難病「NF」の分子レベルの研究は、癌の研究に比べて、ずっと日が浅い。その上、NF患者の総数が、癌患者全体の数に比べて、極めて少数(1%以下)であることから、NFを研究しようという学者の数が極端に少ないばかりか、その研究を支援しようとする政府や民間の資金源が極めて乏しい。
だから、1998年になって、NF1腫瘍の増殖には、PAKという酵素(キナーゼ)が必須であると分かっても、誰もPAK遮断剤をすぐ開発しようとは、しなかった。メルボルンにある我々の研究グループが「PAK遮断剤」を本格的に開発し始めたのは、数年前(今世紀に入って)、過半数の癌の増殖にも、同じキナーゼが必須であることを突き止めてからのことである。そして、ごく最近になって、我々の手で、NF2腫瘍の増殖にも、PAKが必須であることが証明された。しかしながら、開発中の合成「PAK遮断剤」が市販されるまでには、延々10年近くかかる「治験」を経る必要がある。
従って、現在NFに苦しんでいる大多数の患者をできるだけ早く救うためには、市販されている (安全が保証されている)「健康食品サプルメント」製品の中から、有効な「PAK遮断剤」(食材)を緊急に開発することが、自ずから切望されている。そこで我々は、2006年の春以来、かような研究を欧州の「NF研究のメッカ」であるUKE(ハンブルグ大学病院)で開始したわけである。幸い、2007年の初夏に、ニュージーランド産の水溶性プロポリス・エキス、「Bio 30」がNFに有効であることが動物実験で証明され、NF患者を対象とする治験が、欧米や日本を中心に、我々の手で始められるようになった。
日本を含めてアジア諸国では、欧米と違って、NF患者たちは病気そのもの以外にもう1つの苦しみを今なお味わされている。それはNF患者やその家族に対する(社会にはびこる)陰湿な偏見や差別待遇である。その昔、(感染症である)結核、梅毒、ハンセン氏病などに苦しむ患者たちが社会から差別待遇を長らく受けていた。現在は医学の進歩のおかげで、これらの感染症は根治が可能になり、差別も影を潜めた。しかしながら、NF特効薬はまだ市販されておらず、さらにNF腫瘍の一種である皮膚にできる多発性腫瘍を「感染性」のおデキなどと勘違いしている無知な人々がインテリの中にも多く、NF患者あるいはその家族が就職や結婚の際、NFを理由にしばしば不正に、職場から追い出されたり、婚約が破棄されるケースが多い。
かような「無知と偏見からくる差別」を、日本の社会からできるだけ早く一掃するための運動の一環として、2005年の秋、我々有志がNPO「NF CURE Japan」をスタートさせた。NF腫瘍は癌と同様、単に遺伝子の変異によって起こる病気である。もし仮に、家族に癌患者がいるからという理由で、就職や結婚を制限したら、日本社会で職や伴侶を得られる者は、ほとんどいなくなるだろう (平均3、4人に一人は、一生に一度は癌にかかるからだ)。一億失職、一億独身で、日本民族はたちまち亡びるだろう。全く同じ理由で、NF患者やその家族から、職場や結婚のチャンスを取り上げる権利は、誰にもないのである。むしろ、我々健康人に代わって (3千人に一人の割合で)、「貧乏クジ」を引いてくれたNF患者たちに、感謝と労りの気持を抱いて接すべきだろう。それができない連中は (日本を滅亡させる)「人間のクズ」に等しいと、私は思っている。
さて、ジェーンの不可解な難病が、実はNF2であることが初めて判明したのは、1996年になってからで、NF1とNF2との区別がはっきりしてから、既に10年近い月日が経っていた。なお、ジェーンの脳腫瘍が初めて発見された1969年には、「NF2」という難病の概念は、医学の世界にまだなかった。以下は、今から12年前の脳手術(4回目)に関するストーリー(抜粋)である。
1995年2月、父さんが死んだのち、母さんは「独り暮らしはごめんだ」と言い始めた。そこで、私も母さんもそれぞれ、家や家具などを売り払い、その年の8月、アイオワ州の西バーリントンにある小さな家を買った(掃除が簡単になった!)。そして、私のために、通路にてすりを付けてもらった。私はまだ、杖なしに歩いていたが、それがだんだんきつくなり始めていたからだ。てすりのおかげで、歩行がずっと楽になった。
まもなく、10月になって、私がオルガン奏者として働いていた教会の牧師がとうとう亡くなった。私のよき親友だった。11月に私は、新しい車を買った。その一週間後に、我々3人(父さん、母さん、私)が売り払った要約会社の新しい経営者陣から、会社を売却したから、従業員を全員解雇したと言われた。彼らは、母さんと私に、最後の給料を払ったのち、首にした。たった2週間前の通告しかくれなかった。我々は皆、とても裏切られた気持になった。不幸中の幸いは、要約業者で競争相手だった会社に、私が顔を出したら、その場で、私を雇ってくれたことだった。この会社はその昔、父さんや母さんが働いていたところだった。その後、1963年に両親がそこから独立して、自分たちの会社を始めたという面白いいきさつがあった。ある意味で、一周回って、元の古巣に戻ってきたという感じだ。新しい職場では、給料も増えたし、色々な恩恵があった。その1つは、グループ健康保険で、次の私の手術代をカバーしてくれた。私は新しい上司に、聴覚と平均感覚を失いつつあり、いつかはつんぼになり、杖をついて歩かねばならなくなる日が来ることを、予め話した。それでも、彼は私を採用してくれた。彼はとても善良な人間だった! だから、彼と仕事をするのが好きになった。
1996年の夏、補聴器を交換するために、何度もUIHC(アイオワ大学ヘルスセンター)に通院し始めた。晩夏に、とうとう私の聴覚が消えかかってきたので、眼科、OTO科、脳外科など色々な分野の医者たちから精密検査を受けた。そして結局、長らく患っていた私の病気が、なんと稀少難病「NF2」 (神経線維腫症2型)であると宣告された。私はショックを受けたいうよりは、むしろホッとした。というのは、なぜ私に脳腫瘍があり、平均感覚や聴覚が失われたのかが、はっきりし始めたからだ。ショックはあとでやってきた。ジワジワと身体を衰弱させる「不治」の (いまだに根治の方法が見つかっていない) 病であることが、わかったからだ。
母さんが私の4度目の脳手術についてきてくれた。それはその年の11月、私の孫ジェーソン2世が生まれてから8日後のことだった。 私はABI(聴覚脳幹インプラント、俗称「電子耳」)の挿入に同意した。ABIは当時まだ試験的なもので、UIHCでは私が3人目のモルモットだった。聴神経上の腫瘍が脳外科医のアーノルド・メネゼス博士によって除去されたのち、OTO医師ブルース・ガンツ博士によって、ABIが移植されることになった。
15時間半の手術後、ICU (集中治療室) にいる間、私は両足に感覚が全くなかった。一時的に腰から下が麻痺していた。もちろん、私は吐き気をもよおした。この吐き気は、今や脳手術後の自然現象になってしまった! 「 脳の中に挿入されたABIの位置が変わらぬように、できるだけ直立したまま吐くように」と医者から忠告された。足に感覚がないのは、麻酔のせいであることもわかった。 麻酔が切れるまで、かなり時間がかかった。あとで知ったことだが、摘出した腫瘍は1つのみではなく、3つもだった。それで、あんなに手術が長びいたのだ。また左の顔面が部分的に麻痺していた。しばらくして、一部の動きは回復してきたが、他の機能は不可逆的に失われた。
私が歩行不能になっていたので、両脚の血液循環を促進するための足ポンプを、医師が注文してくれた。明らかに、私はどこへも行けなくなった! 普通の食事もまた食べられなくなった。流動食からベビーフード、そして「ピューレ」へという食生活を、再び繰り返すことになった。看護婦たちが初めて私を散歩に連れ出してくれたとき、私の膝は両方とも、あたかも天に昇っていくかのように感じた。両側から支える看護婦たちに向かって、私は冗談を吐いたものだ。
「私は宇宙飛行士としては失格ね。無重力の世界では歩けないから」
私がまだ入院中に、母さんもぐあいが悪くなり、すぐ下の階に入院することになった。そこで、私は車椅子で、母さんの病室を訪ねた。私の脳手術から2週間半後に、2人ともそろって退院になった。私はまだ独りでは、歩けなかった。24時間ケアが必要だった。それに、2、3週間、物療(フィジオ)が必要だと、医師たちに忠告された。
2週間以内に、手術のために母さんがまた病院に戻らざるをえなくなった。そこで、母さんが数人の友達に頼んで、私のケア(看護)をアレンジしてくれた。私は、まだ歩行が不自由だったので、独りぼっちにはしておけなかったからだ。母さんの手術はうまくいった。そして、私も松葉杖をつけば、トイレまで独りで行けるようになった。しかしながら、前かがみがまだできなかったので、用を済ませた後、自分の始末ができず、友人の手をわずらわせざるを得なかった。
やがて、杖を頼りに独りで歩けるようになったので、毎日2時間の散歩を始めた。
これが我々多くのNF2患者の健康回復への道筋だった。とても時間がかかる。その間 (半年ほど)、我々は給料なしになり、最小限の生活を余儀なくされる。その後、フルタイムで働き始め、また車を運転し始める。しかし、7年後に訪れた(最後の)手術は、私の人生を「永遠」(不可逆的)に変えることになる。。。
解説: 「NF」(多発性神経線維腫)の発見から、治療薬の開発まで
通称「レック」(正式には、「レックリングハウゼン氏病」あるいは「NF1」) の最初の発見者は、ドイツの病理学者、フリードリッヒ・フォン・レックリングハウゼン(1833ー1910)である。彼は有名な病理/生理学者ルドルフ・ヴィルショウ(1821ー1902)の弟子の一人であるが、ストラスブルグ大学の学長をやっていた1882年に、この難病を初めて発見し、「皮膚の多発性線維腫と多発性神経腫との関係について」 という題名の歴史的な論文を発表した。
従って、2007年は、この難病の発見から125年目を迎えることになる。そろそろ、この難病の治療(特効)薬が開発され、市販されても、不思議ではない、と素人、特にこの難病に始終悩まされている患者たちやその家族が期待するのは無理からぬことである。しかしながら、その現実はかなり厳しい。
まずその病因が判明するまで、遅々として1世紀以上かかったからである。まず類似したように見える2種類のNF、つまりNF1とNF2との遺伝学的な区別がはっきり確立したのが1987年だった。当時、ボストンのハーバード大学付属病院、マサチューセッツ総合病院(MGH)勤務のバーント・サイジンガーらが、NF1病因遺伝子は、17番目の染色体にあり、NF2病因遺伝子は、22番目の染色体にあることを、初めてつきとめた。
NF2(神経線維腫症 2型)とは何か?
NF2は、シュワノーマ (神経鞘腫) とメニンジオーマ(髄膜腫)に代表される神経あるいは脳腫瘍を伴う難病で、その病因は、NF2と呼ばれる一対の遺伝子の両方が不活性化され、その遺伝子産物である「メルリン」と呼ばれる抗癌蛋白が正常な機能を発揮できなくなることによる。NF2患者の約半数は、親からの遺伝(つまり、片方の親のNF2遺伝子に変異があると、50%の確率で、その変異が子にも遺伝する)。他の半数は「孤発」といって、親の遺伝子状態とは無関係に、受精の初期に起こったNF2遺伝子上の変異によって発症する。NF2の発症頻度は、人口約3万人に1人といわれている。だから、稀少難病の1つと数えられている。
NF2の診断に今日最もよく使われている標準的な症状は、両側性前庭神経鞘腫 (シュワノーマ) である。最初の典型的な前駆症状は、耳鳴り、難聴、平均感覚の消失、視力の低下あるいは2重映像などである。最終的な判断には、NF2遺伝子診断や脳あるいは背骨のMRI診断などの精密検査が必要になる場合がある。
例えば、頻繁に視神経に障害をもたらす脳腫瘍「メニンジオーマ」の場合、半数以上はNF2であるが、残りの半数近くは、全く別の病因であることがわかっている。また、NF2患者の場合、健康人に比べて、アスベストによる悪性中皮腫(肺癌)の発生率が2倍以上になることが、最近報告されている。
NF2は、類似の稀少難病であるNF1(神経線維腫症 1型)とどう違うのだろうか? まずNF1は、カフェオレ班 (コーヒー色の斑点で腫瘍ではない!)、あるいはニューロフィブローマ(神経線維腫)やMPNST(悪性末梢神経鞘腫) に代表される表皮、内皮あるいは神経に発症する腫瘍を伴う難病である。さらに、NF1の病因は、NF1と呼ばれる一対の遺伝子の両方が不活性化され、その遺伝子産物(「RAS GAP」の一種で、抗癌蛋白)が、正常な機能を発揮できなくなることによる。NF1の発症頻度は、人口約3千人に1人といわれている。だから、NF2の発症頻度の10倍ほど高い。NF1の大半(9割)は、良性腫瘍で命に別状はないが、MPNSTを含む残りの1割は、死に至る悪性腫瘍(癌)である。MPNSTの5年生存率は、20%前後といわれている。
1990年になって、そのNF1「病因遺伝子」が単離された。つまり、NF1という抗癌遺伝子が変異によって、その機能を失うと、この難病に伴う種々の神経線維腫(NF)が発症しやすくなるということが判明した。更に、NF2の病因遺伝子である別の抗癌遺伝子(NF2)が、1993年になって単離された。従って、この難病「NF」の分子レベルの研究は、癌の研究に比べて、ずっと日が浅い。その上、NF患者の総数が、癌患者全体の数に比べて、極めて少数(1%以下)であることから、NFを研究しようという学者の数が極端に少ないばかりか、その研究を支援しようとする政府や民間の資金源が極めて乏しい。
だから、1998年になって、NF1腫瘍の増殖には、PAKという酵素(キナーゼ)が必須であると分かっても、誰もPAK遮断剤をすぐ開発しようとは、しなかった。メルボルンにある我々の研究グループが「PAK遮断剤」を本格的に開発し始めたのは、数年前(今世紀に入って)、過半数の癌の増殖にも、同じキナーゼが必須であることを突き止めてからのことである。そして、ごく最近になって、我々の手で、NF2腫瘍の増殖にも、PAKが必須であることが証明された。しかしながら、開発中の合成「PAK遮断剤」が市販されるまでには、延々10年近くかかる「治験」を経る必要がある。
従って、現在NFに苦しんでいる大多数の患者をできるだけ早く救うためには、市販されている (安全が保証されている)「健康食品サプルメント」製品の中から、有効な「PAK遮断剤」(食材)を緊急に開発することが、自ずから切望されている。そこで我々は、2006年の春以来、かような研究を欧州の「NF研究のメッカ」であるUKE(ハンブルグ大学病院)で開始したわけである。幸い、2007年の初夏に、ニュージーランド産の水溶性プロポリス・エキス、「Bio 30」がNFに有効であることが動物実験で証明され、NF患者を対象とする治験が、欧米や日本を中心に、我々の手で始められるようになった。
日本を含めてアジア諸国では、欧米と違って、NF患者たちは病気そのもの以外にもう1つの苦しみを今なお味わされている。それはNF患者やその家族に対する(社会にはびこる)陰湿な偏見や差別待遇である。その昔、(感染症である)結核、梅毒、ハンセン氏病などに苦しむ患者たちが社会から差別待遇を長らく受けていた。現在は医学の進歩のおかげで、これらの感染症は根治が可能になり、差別も影を潜めた。しかしながら、NF特効薬はまだ市販されておらず、さらにNF腫瘍の一種である皮膚にできる多発性腫瘍を「感染性」のおデキなどと勘違いしている無知な人々がインテリの中にも多く、NF患者あるいはその家族が就職や結婚の際、NFを理由にしばしば不正に、職場から追い出されたり、婚約が破棄されるケースが多い。
かような「無知と偏見からくる差別」を、日本の社会からできるだけ早く一掃するための運動の一環として、2005年の秋、我々有志がNPO「NF CURE Japan」をスタートさせた。NF腫瘍は癌と同様、単に遺伝子の変異によって起こる病気である。もし仮に、家族に癌患者がいるからという理由で、就職や結婚を制限したら、日本社会で職や伴侶を得られる者は、ほとんどいなくなるだろう (平均3、4人に一人は、一生に一度は癌にかかるからだ)。一億失職、一億独身で、日本民族はたちまち亡びるだろう。全く同じ理由で、NF患者やその家族から、職場や結婚のチャンスを取り上げる権利は、誰にもないのである。むしろ、我々健康人に代わって (3千人に一人の割合で)、「貧乏クジ」を引いてくれたNF患者たちに、感謝と労りの気持を抱いて接すべきだろう。それができない連中は (日本を滅亡させる)「人間のクズ」に等しいと、私は思っている。
癌のブドウ療法(Grape Cure)
1916年に、当時40歳だった南ア出身の(自然療法)女医ジョアナ・ブラントは、母親が癌で死んでからまもなく、自分も胃癌にかかっていることを知った。まずアプトン・シンクレア著「断食療法」(1911年)を試みたが、彼女の癌には効果がなかった。そこで、断食と食餌療法を適当に組み合わせることによって、何とか癌を根治しようと色々試みた。その結果、肉食は癌の増殖を促すが、菜食は癌の増殖を抑えることにまず気づいた。さらに、特にどんな野菜や果物が癌の抑制に寄与するかを検討した結果、赤ブドウ療法が一番良いという結論を9年間にわたる研究によって得た。彼女は1928年に(南アから米国に移民して、ニューヨーク郊外に「ハーモニー・センター」という食餌療法センターを設立後まもなく)、「天然(化学肥料を使わないで)栽培した赤や紫色のブドウの絞り汁を毎日飲んで、自分の胃癌を根治した」という体験を「(癌の)ブドウ療法」(The Grape Cure) というタイトルで、100ページ弱の本にして出版した。その後、彼女は40年以上、健康な生活を全うしたそうである。
ここでは、そのごくエッセンス(さわり)だけを手短かに紹介するにとどめる。
準備(断食): この食餌療法の直前に、2、3日間の断食を勧める。その期間、冷たい水や新鮮なレモンの絞り汁を十分に飲んでもらいたい。この断食は、胃袋を空っぽにすることによって、ブドウへの食欲を増進することに役立つ。
断食後: 朝一番にグラスに1、2杯の冷たい水を飲む。
本番(ブドウ療法): できれば午前8時から午後8時まで、2ー3時間毎に、赤ブドウだけを丸ごと、あるいはジュースにして、皮も含めてよく噛んで飲み込む。この食餌療法を1、2週間続ける。
分量: 少量から一日毎に2倍づつ量を増やしていき、最終的には、日毎に0。5キロから2キロまで、試してみるとよい。ただし、食欲がないのに、無理矢理にブドウ(汁)を摂取するのは避けたい。食欲とよく相談しながら量と回数(日に5ー7食)を決めよう。
さて、この赤ブドウ汁の中にある抗癌作用を持つ物質は一体何だろうか? 以後70年以上の月日をかけて、多くの学者によって、「ブドウ療法」の科学的根拠を探る研究がなされた。ようやく1997年になって、米国シカゴにあるイリノイ大学のジョン・ペズットのグループによって、その抗癌物質が「レズベラトロル」というポリフェノールの一種(R3、水酸基を3つ持つスチルベン)であることがつき止められた。
「R3」は、赤ブドウの主に果皮の部分に含まれている。従って、この果皮を使って作られる赤ワインにはR3が豊富だが、(赤い果皮を使わない) 白ワインにはR3がほとんど含まれていない。従って、赤ワインを適度に飲めば、癌の予防や治療に役立つと考えられる。そこで、(子供向けには)グレープジュース、(大人向けには「赤ワインを適度に飲んで、健康的な新年を迎えよう! と年賀状に書くことにした。
さて、2002年に英国のライセスターにあるデュモンフォート大学のジェリーポッターのグループにより、R3は癌細胞内に豊富にある酵素の働きによって、さらに水酸化されて、より制癌作用の強い「ピシアタノル」(R4)という誘導体に変化することがわかった。正常細胞にはこの酵素が少ないので、R3は癌細胞の増殖を選択的に抑制することができる。それでは、R4はいかなるメカニズムで、癌細胞の増殖を抑えるのだろうか?
1994年に米国ニューメキシコ大学のジャネット・オリバーのグループによって、R4がチロシンキナーゼの一種である「SYK」を特異的に阻害することが明らかにされていた。さらに1997年になって、米国ロチェスターにあるメイヨー病院のポール・リスボンのグループによって、この「SYK」がPIー3 キナーゼの活性化に必要であることが発見された。従って、R4は最終的にはPIー3 キナーゼの下流にあるキナーゼ、PAKやAKTなどの活性化を遮断することが、2002年に米国のフロリダ州にあるリー・モフィット癌センターのジュリー・デュジューのグループによって、実際に証明された。
ここでは、そのごくエッセンス(さわり)だけを手短かに紹介するにとどめる。
準備(断食): この食餌療法の直前に、2、3日間の断食を勧める。その期間、冷たい水や新鮮なレモンの絞り汁を十分に飲んでもらいたい。この断食は、胃袋を空っぽにすることによって、ブドウへの食欲を増進することに役立つ。
断食後: 朝一番にグラスに1、2杯の冷たい水を飲む。
本番(ブドウ療法): できれば午前8時から午後8時まで、2ー3時間毎に、赤ブドウだけを丸ごと、あるいはジュースにして、皮も含めてよく噛んで飲み込む。この食餌療法を1、2週間続ける。
分量: 少量から一日毎に2倍づつ量を増やしていき、最終的には、日毎に0。5キロから2キロまで、試してみるとよい。ただし、食欲がないのに、無理矢理にブドウ(汁)を摂取するのは避けたい。食欲とよく相談しながら量と回数(日に5ー7食)を決めよう。
さて、この赤ブドウ汁の中にある抗癌作用を持つ物質は一体何だろうか? 以後70年以上の月日をかけて、多くの学者によって、「ブドウ療法」の科学的根拠を探る研究がなされた。ようやく1997年になって、米国シカゴにあるイリノイ大学のジョン・ペズットのグループによって、その抗癌物質が「レズベラトロル」というポリフェノールの一種(R3、水酸基を3つ持つスチルベン)であることがつき止められた。
「R3」は、赤ブドウの主に果皮の部分に含まれている。従って、この果皮を使って作られる赤ワインにはR3が豊富だが、(赤い果皮を使わない) 白ワインにはR3がほとんど含まれていない。従って、赤ワインを適度に飲めば、癌の予防や治療に役立つと考えられる。そこで、(子供向けには)グレープジュース、(大人向けには「赤ワインを適度に飲んで、健康的な新年を迎えよう! と年賀状に書くことにした。
さて、2002年に英国のライセスターにあるデュモンフォート大学のジェリーポッターのグループにより、R3は癌細胞内に豊富にある酵素の働きによって、さらに水酸化されて、より制癌作用の強い「ピシアタノル」(R4)という誘導体に変化することがわかった。正常細胞にはこの酵素が少ないので、R3は癌細胞の増殖を選択的に抑制することができる。それでは、R4はいかなるメカニズムで、癌細胞の増殖を抑えるのだろうか?
1994年に米国ニューメキシコ大学のジャネット・オリバーのグループによって、R4がチロシンキナーゼの一種である「SYK」を特異的に阻害することが明らかにされていた。さらに1997年になって、米国ロチェスターにあるメイヨー病院のポール・リスボンのグループによって、この「SYK」がPIー3 キナーゼの活性化に必要であることが発見された。従って、R4は最終的にはPIー3 キナーゼの下流にあるキナーゼ、PAKやAKTなどの活性化を遮断することが、2002年に米国のフロリダ州にあるリー・モフィット癌センターのジュリー・デュジューのグループによって、実際に証明された。
2008年4月21日月曜日
『グリーン党の生みの親』(Bob Brown)
南氷洋での日本による「偽装の調査」捕鯨は、豪州(労働党)政府や野党の保守連合、グリーン党などからの強い抗議や、グリーンピースやシー・シェパードによる活発な(妨害)海上作戦により、結局、捕獲数が目標の半分に終わった。私はグリーン党支持者の一人で、党首のボッブ・ブラウン医師に信服している。世界に先駆けて、豪州タスマニア島から、自然保護をめざして「グリーン党」を打ち上げたボッブ・ブラウン(上院議員)をご存知だろうか?
ケニアのワンガリ・マータイや米国のアル・ゴアが植林運動ヤ地球温暖化をそれぞれ唱え始める以前から、彼は自然保護問題を政界に訴え始めたパイオニアである。その彼の英文伝記「Gentle Revolutionary」(直訳すれば、「やさしい革命家」、約250ページ) が2年前に出版された。
昨年11月末の(豪州)総選挙で、グリーン党のバックアップを受けて、(保守連合から11年ぶりに政権を奪回した)労働党(ケビン・ラッド政府)は、いち早く京都議定書に署名し、最近バリ島で開催された国連主催の「温暖化防止」会議では、リーダーシップを発揮して、京都議定書の署名をいまだに拒んでいる米国(中国と共に、世界で炭酸ガスを最も多量に放出している国)に、積極的に圧力をかけ始めている。さらに、(グリーン党の主張に基づいて)豪州は挙国一致で、日本による野蛮な「捕鯨侵略」に対する活発な抗議行動を、南氷洋上で成功させた。今や豪州は「グリーン」(自然/環境保護)運動の「台風の目」になりつつある。その起源(原動力)である情熱家「ボブ・ブラウン」の(草の根)グリーン運動の生い立ちを知ることは、今世紀の「市民による地球温暖化防止」運動を成功させる重要な「鍵」である。
(ドイツと違って)日本では、「下からのグリーン運動」がうまく育っていない。例えば、2004年の参議院選で、いわゆる「緑の党」の党首「紋次郎」がとうとう落選し、党自体を解散してしまった(その後、みどりの「会議」が、みどりの「テーブル」に縮小)! 従って、日本の「土壌」と市民の「意識」を共に向上させることが、「グリーン」の木を育てるために急務である。
総選挙が目前に迫る!
http://www.asahi.com/politics/update/0420/TKY200804200195.html
ごく最近、福田内閣への支持率がとうとう25%にまで凋落し、前回の参議院選直前の安倍内閣への支持率26%をも下回った。従って、今夏(サミット後)の「国会解散」は必至であろう。そして、野党各党が団結すれば、与党の衆議院選挙での大敗も視界内にある。もし(十数年前のごとく)野党が再び天下を取れば、「グリーン」支持層の声も内閣の政策にもっと反映されるチャンスが出てくるだろう。「環境保護/改善のため、グリーンよ、再起せよ!」
ケニアのワンガリ・マータイや米国のアル・ゴアが植林運動ヤ地球温暖化をそれぞれ唱え始める以前から、彼は自然保護問題を政界に訴え始めたパイオニアである。その彼の英文伝記「Gentle Revolutionary」(直訳すれば、「やさしい革命家」、約250ページ) が2年前に出版された。
昨年11月末の(豪州)総選挙で、グリーン党のバックアップを受けて、(保守連合から11年ぶりに政権を奪回した)労働党(ケビン・ラッド政府)は、いち早く京都議定書に署名し、最近バリ島で開催された国連主催の「温暖化防止」会議では、リーダーシップを発揮して、京都議定書の署名をいまだに拒んでいる米国(中国と共に、世界で炭酸ガスを最も多量に放出している国)に、積極的に圧力をかけ始めている。さらに、(グリーン党の主張に基づいて)豪州は挙国一致で、日本による野蛮な「捕鯨侵略」に対する活発な抗議行動を、南氷洋上で成功させた。今や豪州は「グリーン」(自然/環境保護)運動の「台風の目」になりつつある。その起源(原動力)である情熱家「ボブ・ブラウン」の(草の根)グリーン運動の生い立ちを知ることは、今世紀の「市民による地球温暖化防止」運動を成功させる重要な「鍵」である。
(ドイツと違って)日本では、「下からのグリーン運動」がうまく育っていない。例えば、2004年の参議院選で、いわゆる「緑の党」の党首「紋次郎」がとうとう落選し、党自体を解散してしまった(その後、みどりの「会議」が、みどりの「テーブル」に縮小)! 従って、日本の「土壌」と市民の「意識」を共に向上させることが、「グリーン」の木を育てるために急務である。
総選挙が目前に迫る!
http://www.asahi.com/politics/update/0420/TKY200804200195.html
ごく最近、福田内閣への支持率がとうとう25%にまで凋落し、前回の参議院選直前の安倍内閣への支持率26%をも下回った。従って、今夏(サミット後)の「国会解散」は必至であろう。そして、野党各党が団結すれば、与党の衆議院選挙での大敗も視界内にある。もし(十数年前のごとく)野党が再び天下を取れば、「グリーン」支持層の声も内閣の政策にもっと反映されるチャンスが出てくるだろう。「環境保護/改善のため、グリーンよ、再起せよ!」
「オバマ: ホワイトハウスへの道」 (Obama)
バラク・オバマの自伝(回顧録)が既に2冊出版され、全米でベストセラーになっているが、この本 (Obama: from Promise to Power) by David Mendell (2007) は、カリスマ的な次期大統領候補「オバマ」に関する初の(客観的)評伝。ダイヤモンド社は、オバマの最初の自伝(邦訳:マイ・ドリーム、政治家になる前の半生記)を絶好のチャンス(年末)に出版して、「先見の明」を示した。この評伝の邦訳を、もし (大統領選直後の) 来たる年末に出版できれば、タイミングとして最高であろう。
米国の心ある市民たちは、ジョージ・ブッシュ政権による8年にわたる暗黒時代から、できるだけ早く抜け出して、誇りべき国の再建を切望している。そのためには、全く新しいタイプの指導者の出現が待ち望まれている。そこに彗星(あるいは救世主)のごとく忽然と米国の政界に登場してきたのが、バラク・オバマという人物である。白人の母とケニア出身の父を持つオバマは、ハワイ生まれだが、 少年時代をインドネシアで過ごすという異例の体験を持つ。父親はハーバード大学で学ぶが貧困のため、妻子を米国に残して、ケニアに帰国する。従って、オバマは母や母方の祖母のもとで、青春時代を過ごすことになる。のちにハーバード大学で法律を勉強し、弁護士として、シカゴの貧民窟に住む黒人たちの福祉向上のために働き始める。そして、彼らを代表して、イリノイ州の下院議員に当選して、政界で活躍し始める。オバマが脚光を浴び始めたのは、2002年末にイラク戦争に反対して、抗議運動の先頭に立った頃からである。
2004年の夏には、民主党の大統領候補にジョン・ケリーを選出する際、基調演説を引き受け、「米国市民全体の団結」を呼びかけ、若者やインテリ層から注目を集め、2008年の大統領候補として、担ぎ上げられ始めた。そして、その踏み台として、2004年末の総選挙では、イリノイ州選出の上院議員として、初当選を果たす。2007年の2月には、とうとう大統領選に出馬を決心する。カリスマ的な雄弁に物を言わせ、丸1年後の2008年の2月には、長らく本命と目されていたヒラリー・クリントン上院議員を押し退けて、とうとう民主党の大統領候補のトップに踊り出るという快挙を成し遂げる。1960年代に活躍したケネディー兄弟(ジャックとロバート)の再来と目されている。2008年の11月における、共和党候補ジョン・マケインとの一騎討が大いに期待されている。
面白いことにオバマ家は夫妻共、名門ハーバード大学出の弁護士、クリントン家は夫妻共、名門エール大学出の弁護士。従って、オバマ家とクリントン家が仲良く「大統領ー副大統領」チームを組めば、海軍兵学校卒の老軍人であるマケイン候補など一網打尽となるだろう。
オバマ自身の言葉によれば、彼の大志の出どころは、(他界した)父親の期待に答えるばかりではなく、父親の犯した失敗を繰り返すまいとする努力にあると。
貧困や差別に苦しむ多くの人々の生活をより良くするために、自分の素質をフルに生かして 社会奉仕をすることが、彼の生涯の夢である。
この評伝は、 彼を巡る様々な環境下 (ハワイ、インドネシア、ロサンゼルス、ニューヨーク、ボストン、シカゴ、ワシントン) で、オバマが有色人種として初の大統領になるべき優れた素質を、いかに築き上げてきたか、その異例な知的成長の軌跡を、我々読者に雄弁に語りかけてくれる。
目次
1。 政界のスター誕生
2。 母親の夢
3。 ハワイ生まれの素朴な少年「バリー」
4。 コロンビア大学時代
5。 シカゴで社会奉仕
6。 ハーバード大学の優等生「バラク」
7。 ミシェルとの結婚
8。 州議会にデビュー
9。 大失敗
10。 作戦の立て直し
11。 戦闘準備
12。 イラク戦争 (侵略) に反対
13。 上院挑戦への第一歩
14。 政治的信条と女性ファン
15。 民主党内のライバル
16。 テレビ広告 (IT) の威力
17。 最初のハードルを突破
18。 中道左派路線
19。 共和党候補ライアンとの対決
20。 民主党大会での大飛躍
21。 上院議員に初当選
22。 大統領選への出馬準備
23。 南ア訪問
24。 ケニア訪問
25。 父親の故郷
26。 ホワイトハウスへの道
米国の心ある市民たちは、ジョージ・ブッシュ政権による8年にわたる暗黒時代から、できるだけ早く抜け出して、誇りべき国の再建を切望している。そのためには、全く新しいタイプの指導者の出現が待ち望まれている。そこに彗星(あるいは救世主)のごとく忽然と米国の政界に登場してきたのが、バラク・オバマという人物である。白人の母とケニア出身の父を持つオバマは、ハワイ生まれだが、 少年時代をインドネシアで過ごすという異例の体験を持つ。父親はハーバード大学で学ぶが貧困のため、妻子を米国に残して、ケニアに帰国する。従って、オバマは母や母方の祖母のもとで、青春時代を過ごすことになる。のちにハーバード大学で法律を勉強し、弁護士として、シカゴの貧民窟に住む黒人たちの福祉向上のために働き始める。そして、彼らを代表して、イリノイ州の下院議員に当選して、政界で活躍し始める。オバマが脚光を浴び始めたのは、2002年末にイラク戦争に反対して、抗議運動の先頭に立った頃からである。
2004年の夏には、民主党の大統領候補にジョン・ケリーを選出する際、基調演説を引き受け、「米国市民全体の団結」を呼びかけ、若者やインテリ層から注目を集め、2008年の大統領候補として、担ぎ上げられ始めた。そして、その踏み台として、2004年末の総選挙では、イリノイ州選出の上院議員として、初当選を果たす。2007年の2月には、とうとう大統領選に出馬を決心する。カリスマ的な雄弁に物を言わせ、丸1年後の2008年の2月には、長らく本命と目されていたヒラリー・クリントン上院議員を押し退けて、とうとう民主党の大統領候補のトップに踊り出るという快挙を成し遂げる。1960年代に活躍したケネディー兄弟(ジャックとロバート)の再来と目されている。2008年の11月における、共和党候補ジョン・マケインとの一騎討が大いに期待されている。
面白いことにオバマ家は夫妻共、名門ハーバード大学出の弁護士、クリントン家は夫妻共、名門エール大学出の弁護士。従って、オバマ家とクリントン家が仲良く「大統領ー副大統領」チームを組めば、海軍兵学校卒の老軍人であるマケイン候補など一網打尽となるだろう。
オバマ自身の言葉によれば、彼の大志の出どころは、(他界した)父親の期待に答えるばかりではなく、父親の犯した失敗を繰り返すまいとする努力にあると。
貧困や差別に苦しむ多くの人々の生活をより良くするために、自分の素質をフルに生かして 社会奉仕をすることが、彼の生涯の夢である。
この評伝は、 彼を巡る様々な環境下 (ハワイ、インドネシア、ロサンゼルス、ニューヨーク、ボストン、シカゴ、ワシントン) で、オバマが有色人種として初の大統領になるべき優れた素質を、いかに築き上げてきたか、その異例な知的成長の軌跡を、我々読者に雄弁に語りかけてくれる。
目次
1。 政界のスター誕生
2。 母親の夢
3。 ハワイ生まれの素朴な少年「バリー」
4。 コロンビア大学時代
5。 シカゴで社会奉仕
6。 ハーバード大学の優等生「バラク」
7。 ミシェルとの結婚
8。 州議会にデビュー
9。 大失敗
10。 作戦の立て直し
11。 戦闘準備
12。 イラク戦争 (侵略) に反対
13。 上院挑戦への第一歩
14。 政治的信条と女性ファン
15。 民主党内のライバル
16。 テレビ広告 (IT) の威力
17。 最初のハードルを突破
18。 中道左派路線
19。 共和党候補ライアンとの対決
20。 民主党大会での大飛躍
21。 上院議員に初当選
22。 大統領選への出馬準備
23。 南ア訪問
24。 ケニア訪問
25。 父親の故郷
26。 ホワイトハウスへの道
神の火を制御せよ (Command the Morning)
来たる8月の原爆記念日に向けて、4日から11日にかけて、大変珍しい方が北京から日本を初めて訪問してくる予定です。
ジョアン・ヒントンという86歳のアメリカ人女性です。息子さんのビルと同伴で来日すると聞いています。彼女は、戦争中、ロスアラモスの砂漠で、史上初の原爆を製造した「マンハッタン計画」チームの一員で、恐らく最後の生存者の一人です。広島および長崎への原爆投下の報を聞いて、(人類の大量破壊をもたらした)原子物理学の研究を辞め、中国大陸に渡り、酪農業を始めながら、毛沢東の中国人民解放運動に参加し、49年の革命後は、反核運動を進めながら、中国農民の生活水準の向上のために、専念していてきたそうです。
さて去年の夏、我々は「神の火を制御せよ 原爆をつくった人びと」という訳本を出版しましたが、それはパール・バック女史が1959年に出版した英文小説「Command the Morning」の邦訳です。この小説は「マンハッタン計画」をドラマ化した「反核」小説ですが、その中に登場する架空の女性、ジェーン・アールのモデルの一人になった人物が、実は、ジョアン・ヒントンだったのです。彼女は、シカゴ大学の(アメ・フット)球場の地下で、42年末に(真珠湾奇襲から丸一年後)、史上初の原子炉を開発した(ノーベル賞受賞者)エンリコ・フェルミの弟子(院生)の一人でした。小説では、ジェーンは原爆投下直前の45年7月下旬に、トルーマン大統領宛ての70名の科学者による請願書(降服寸前の日本に原爆を使わぬよう訴えた署名)にサインします。
しかしながら、実際には、この請願書はシカゴ大学の核物理研究者仲間だけに回覧され、原爆の開発に直接従事していたロスアラモス研究所の(ジョアンを含めた)科学者の間には、所長のロバート・オッペンハイマーによって回覧がブロックされたため、現場の連中は誰も署名ができなかったのです。実際に署名した良心的な70名の中には、少なくとも7名の女性研究員(七人の侍)がいました。従って、彼らも(小説中の)ジェーンの精神的シンボルに当然なっているでしょう。
母ジョアンは老弱なので、恐らく今年が広島や長崎の爆心地を訪れ、被爆者たちの霊を弔い、現地の人々と和解をする最後のチャンスになるだろう、と息子のビルは言っています。
果たせるかな、2年後に北京の自宅で彼女は心安らかに永眠の途についた。「マン
ハッタン(原爆開発)計画」に従事した研究者やエンジニアの大部分は、被曝のた
め白血病などの癌で若死にしたが、彼女は例外的に癌にもかからず、米寿(88才)
を全うした。彼女の言によれば、原爆開発中に少なくとも2名の研究者/技師が
大量被曝のため、即死あるいは病死したそうである。もっとも、その事実は今で
も、米国政府の機密情報として公開されていないが、パール・バックの歴史小説
「神の火を制御せよ:原爆を作った人々」には、その被爆死の様子が克明に描かれて
いる。 恐らく、その情報源はジョアン自身ではなかろうか。。。
実は、1940年に冬季オリンピックが「札幌」で開催される予定だったが、戦争
のため中止になった。このオリンピックに、何とジョアンが米国を代表するスキー
選手の一人に選ばれていたのだが、突如中止になり、彼女は戦時中、原子物理学に
専心することになった!
ジョアンは若かりし頃、小説の主人公ジェーンのように乗馬が得意だったそうです。乗馬好きの所長ロバート・オッペンハイマー (小説中のバートのモデル) と時々、ニューメキシコの砂漠を馬で駆け巡ったのではないかと、私は想像したくなります。
ジョアン・ヒントンという86歳のアメリカ人女性です。息子さんのビルと同伴で来日すると聞いています。彼女は、戦争中、ロスアラモスの砂漠で、史上初の原爆を製造した「マンハッタン計画」チームの一員で、恐らく最後の生存者の一人です。広島および長崎への原爆投下の報を聞いて、(人類の大量破壊をもたらした)原子物理学の研究を辞め、中国大陸に渡り、酪農業を始めながら、毛沢東の中国人民解放運動に参加し、49年の革命後は、反核運動を進めながら、中国農民の生活水準の向上のために、専念していてきたそうです。
さて去年の夏、我々は「神の火を制御せよ 原爆をつくった人びと」という訳本を出版しましたが、それはパール・バック女史が1959年に出版した英文小説「Command the Morning」の邦訳です。この小説は「マンハッタン計画」をドラマ化した「反核」小説ですが、その中に登場する架空の女性、ジェーン・アールのモデルの一人になった人物が、実は、ジョアン・ヒントンだったのです。彼女は、シカゴ大学の(アメ・フット)球場の地下で、42年末に(真珠湾奇襲から丸一年後)、史上初の原子炉を開発した(ノーベル賞受賞者)エンリコ・フェルミの弟子(院生)の一人でした。小説では、ジェーンは原爆投下直前の45年7月下旬に、トルーマン大統領宛ての70名の科学者による請願書(降服寸前の日本に原爆を使わぬよう訴えた署名)にサインします。
しかしながら、実際には、この請願書はシカゴ大学の核物理研究者仲間だけに回覧され、原爆の開発に直接従事していたロスアラモス研究所の(ジョアンを含めた)科学者の間には、所長のロバート・オッペンハイマーによって回覧がブロックされたため、現場の連中は誰も署名ができなかったのです。実際に署名した良心的な70名の中には、少なくとも7名の女性研究員(七人の侍)がいました。従って、彼らも(小説中の)ジェーンの精神的シンボルに当然なっているでしょう。
母ジョアンは老弱なので、恐らく今年が広島や長崎の爆心地を訪れ、被爆者たちの霊を弔い、現地の人々と和解をする最後のチャンスになるだろう、と息子のビルは言っています。
果たせるかな、2年後に北京の自宅で彼女は心安らかに永眠の途についた。「マン
ハッタン(原爆開発)計画」に従事した研究者やエンジニアの大部分は、被曝のた
め白血病などの癌で若死にしたが、彼女は例外的に癌にもかからず、米寿(88才)
を全うした。彼女の言によれば、原爆開発中に少なくとも2名の研究者/技師が
大量被曝のため、即死あるいは病死したそうである。もっとも、その事実は今で
も、米国政府の機密情報として公開されていないが、パール・バックの歴史小説
「神の火を制御せよ:原爆を作った人々」には、その被爆死の様子が克明に描かれて
いる。 恐らく、その情報源はジョアン自身ではなかろうか。。。
実は、1940年に冬季オリンピックが「札幌」で開催される予定だったが、戦争
のため中止になった。このオリンピックに、何とジョアンが米国を代表するスキー
選手の一人に選ばれていたのだが、突如中止になり、彼女は戦時中、原子物理学に
専心することになった!
ジョアンは若かりし頃、小説の主人公ジェーンのように乗馬が得意だったそうです。乗馬好きの所長ロバート・オッペンハイマー (小説中のバートのモデル) と時々、ニューメキシコの砂漠を馬で駆け巡ったのではないかと、私は想像したくなります。
我が若かりし日々 (Home)
昔懐かしいミュージカル映画「サウンド・オブ・ミュージック」で大活躍した女優ジュリー・アンドリュースが、自身の若かりし日々を回想しながら、自分の「家庭」で起こった出来事を中心にして、独特なウイットを交えて綴っている。ちなみに、英文原書のタイトルは「ホーム」(我が家)。1935年にロンドンで生まれ、物心ついて最初に口にした言葉がなんと「ホーム」だったそうである。4歳のときに欧州では、ナチスドイツとの戦争が始まっていた。以来6年間、毎日のごとく、ドイツの爆撃機がロンドンの上空に現れ、空爆を繰り返した。彼女は、味方の飛行機と敵機を爆音の違いで、どちらが上空にきていることを聞き分ける特技を備えていた。だから、空襲警報が鳴る前に、敵機の編隊がやって来るやピーッと警笛を鳴らして、近所の人々に、洗濯や料理の最中に、防空壕へ駈け込むべきタイミングを知らせる戦時の特務を母親から与えらえたそうだ。
しかしながら、最初の「ホーム」は余り長続きしなかった。ジュリーが5歳になった頃に、とうとう両親が離婚し、母親バーバラが相棒のオペラ歌手、テッド・アンドリュース(愛称ポップ)と再婚することなる。こうして、新しい父親「ポップ」との第二の「ホーム」が始まった。1945年に第二次世界大戦が終了して間もなく、ジュリーは歌手としての才能を認められ、BBCのテレビショウにデビューする。こうして、彼女の70年近い歌手としてのキャリアがスタートしたのだ。
この回想録は1963年に彼女の最初の娘エマが生後半年のころ、教会で洗礼を受けるところで終わっている。母親になったばかりの本人がまだ28歳のころである。この年に偶々、ジュリーはウオルト・ディズニー映画「メリー・ポピンズ」に主演として初出演し、映画界でも大成功を収める。従って、近い将来、その続編が出版されることは間違いない。それを私は大変楽しみにしている。
しかしながら、最初の「ホーム」は余り長続きしなかった。ジュリーが5歳になった頃に、とうとう両親が離婚し、母親バーバラが相棒のオペラ歌手、テッド・アンドリュース(愛称ポップ)と再婚することなる。こうして、新しい父親「ポップ」との第二の「ホーム」が始まった。1945年に第二次世界大戦が終了して間もなく、ジュリーは歌手としての才能を認められ、BBCのテレビショウにデビューする。こうして、彼女の70年近い歌手としてのキャリアがスタートしたのだ。
この回想録は1963年に彼女の最初の娘エマが生後半年のころ、教会で洗礼を受けるところで終わっている。母親になったばかりの本人がまだ28歳のころである。この年に偶々、ジュリーはウオルト・ディズニー映画「メリー・ポピンズ」に主演として初出演し、映画界でも大成功を収める。従って、近い将来、その続編が出版されることは間違いない。それを私は大変楽しみにしている。
2008年4月20日日曜日
映画「背骨のある男」(Bone Man)
ごく最近、豪州の出版社から「Bone Man of Kokoda」という本が発売された。パプア・ニューギニア(PNG)で25年間、戦友の遺骨を拾い続けた「最後のサムライ」西村 幸吉 氏 (現在、88歳)に関する実話である。一気に読み終った。
著者チャールズ・ハプルはメルボルンに住む(豪州人)新聞記者。主人公である「エンジニア」西村 氏(当時22歳)は、1942年9月に自分の属する(高知県出身者を中心とする)歩兵小隊(56人)と共に、ココダ街道で豪州軍(約千人)と死闘を交え、戦場で自分を除く戦友全員を失う。戦地を離れる瞬間、(もし生還できたら)「戦後、この地に戻ってきて、君たちの霊を弔う」と誓った。
その後、台湾やビルマで死闘を繰り返し、原爆投下の直前に、高知県の病院へ幸い生還する。戦後10年の空白期を経て、ついに上京し、都内で「西村製作所」の営業を始める。「昔の誓い」を果たすため、60歳で会社をキッパリ辞め、息子たちに会社を譲ると共に、全財産を妻に譲り、戦友たちが果てたPNGの戦場に単身戻り、25年間にわたってバラックやテントに住み込み、ひたすら(戦場にちらばる)戦友たちの遺骨や遺品を拾い集め、日本の遺族に届け続けた。さらに、地元のPNG住民たちのために、学校や教会を建てるなどの慈善事業も続け、住民たちとの融和を図った。昔懐かしい映画「ビルマの竪琴」の主人公を想起させる、稀れにみる人物である。ちっぽけな小舟で、日本からPNGまで、嵐をついて、果敢に南海を渡る66歳の元老兵などドラマチックな場面がどっさり、映画化にはピッタリの作品だ。
できればこの夏、帰京の折、埼玉県加須市で娘(幸子)さんと暮らす西村さんに会い、映画化を見越した脚本執筆に関して、相談してみようと思っている。日本国内で邦訳 (本) がどれぐらい売れるかわからないが、(戦争を知らない)若者たちのために、ぜひ映画化したい作品である。「背骨のある男」(bone man)とは、一体どんな人間なのかを、知らしめる感動的な映画にしたい。
著者チャールズ・ハプルはメルボルンに住む(豪州人)新聞記者。主人公である「エンジニア」西村 氏(当時22歳)は、1942年9月に自分の属する(高知県出身者を中心とする)歩兵小隊(56人)と共に、ココダ街道で豪州軍(約千人)と死闘を交え、戦場で自分を除く戦友全員を失う。戦地を離れる瞬間、(もし生還できたら)「戦後、この地に戻ってきて、君たちの霊を弔う」と誓った。
その後、台湾やビルマで死闘を繰り返し、原爆投下の直前に、高知県の病院へ幸い生還する。戦後10年の空白期を経て、ついに上京し、都内で「西村製作所」の営業を始める。「昔の誓い」を果たすため、60歳で会社をキッパリ辞め、息子たちに会社を譲ると共に、全財産を妻に譲り、戦友たちが果てたPNGの戦場に単身戻り、25年間にわたってバラックやテントに住み込み、ひたすら(戦場にちらばる)戦友たちの遺骨や遺品を拾い集め、日本の遺族に届け続けた。さらに、地元のPNG住民たちのために、学校や教会を建てるなどの慈善事業も続け、住民たちとの融和を図った。昔懐かしい映画「ビルマの竪琴」の主人公を想起させる、稀れにみる人物である。ちっぽけな小舟で、日本からPNGまで、嵐をついて、果敢に南海を渡る66歳の元老兵などドラマチックな場面がどっさり、映画化にはピッタリの作品だ。
できればこの夏、帰京の折、埼玉県加須市で娘(幸子)さんと暮らす西村さんに会い、映画化を見越した脚本執筆に関して、相談してみようと思っている。日本国内で邦訳 (本) がどれぐらい売れるかわからないが、(戦争を知らない)若者たちのために、ぜひ映画化したい作品である。「背骨のある男」(bone man)とは、一体どんな人間なのかを、知らしめる感動的な映画にしたい。
登録:
コメント (Atom)